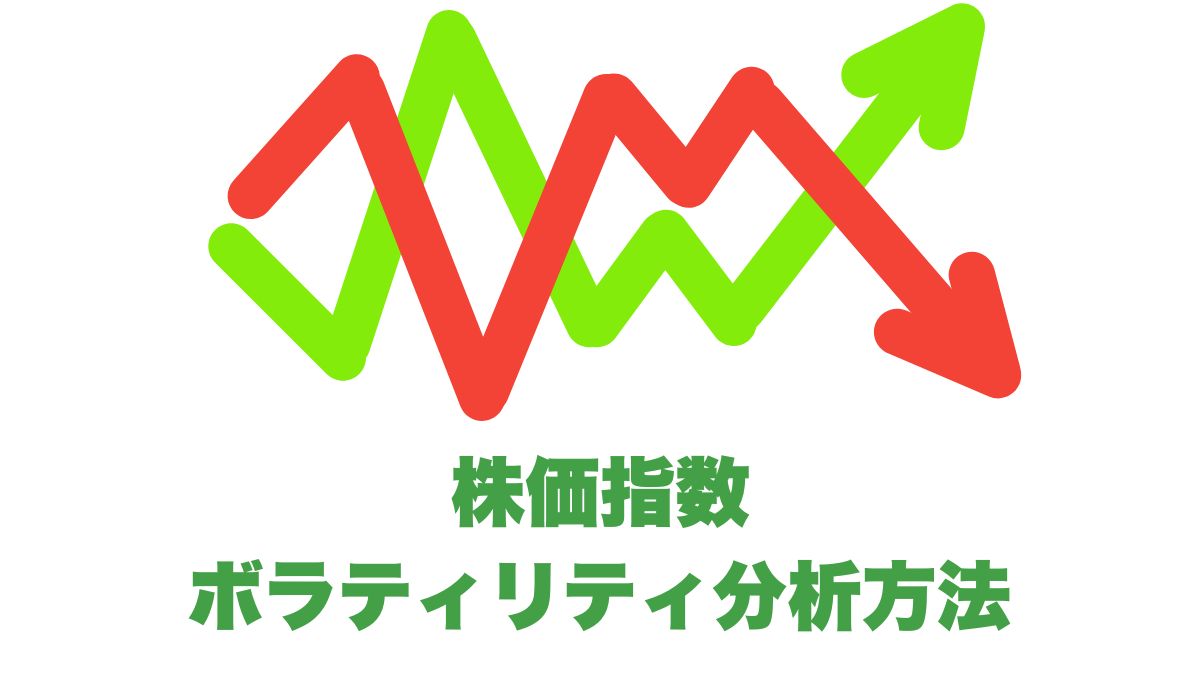
株価指数のボラティリティ分析方法:S&P500・ナスダック・ラッセル2000を比較する
By Staff | 2025-09-06
Category: インデックス投資
株価指数は市場全体の動きを示す代表的な指標ですが、その値動きには必ずリスクが伴います。
投資で注目されるのはリターンばかりになりがちですが、「どれくらいの揺れ幅があるのか」を知ることも長期運用では欠かせません。
ここで重要になるのがボラティリティ、すなわち価格変動の大きさです。
本記事では、ボラティリティの基本から具体的な指数の特徴、計算方法、そして長期投資での活かし方を解説します。
ボラティリティとは?
ボラティリティとは、株価や指数が一定期間にどの程度変動したかを示す数値です。
一般的にはリターンの標準偏差を年率換算して表します。
- ボラティリティが高い:短期間で大きく上がったり下がったりする → リターンの可能性もリスクも大きい
- ボラティリティが低い:値動きが比較的安定 → 成長余地は小さいが安心感がある
米国株インデックスの代表格であるS&P500の長期平均ボラティリティは約15〜20%。
一方でナスダック総合は20〜25%程度、ラッセル2000は25〜30%程度とさらに大きな変動幅を示すことが多いです。
ボラティリティの計算方法をわかりやすく解説
ボラティリティは「値動きの大きさ」を数字にしたものです。
実際には、株価や指数の**日ごとのリターン(上がった%や下がった%)**を集めて、そのバラつきを計算します。
基本的な流れは次の通りです。
日次リターンを計算する
例えばS&P500が100から105に上がったら、
(105-100) ÷ 100 = 0.05(5%)
これがその日のリターンです。リターンの標準偏差を出す
日ごとのリターンのバラつきを計算し、「どれくらい散らばっているか」を数値化します。これが日次ボラティリティです。年率に直す
株式市場は1年でおよそ252営業日あるので、
年率ボラティリティ = 日次ボラティリティ × √252
という式で年換算します。
簡単な例
仮にある株価指数が5日間で以下のように動いたとします:
- 100 → 102(+2%)
- 102 → 101(-1%)
- 101 → 104(+2.9%)
- 104 → 103(-1%)
103 → 106(+2.9%)
このリターンのバラつきを計算すると、日次ボラティリティは約1.5%になります。
これを年率に直すと 1.5% × √252 ≈ 24% です。
つまり、この指数は「1年間でおよそ±24%程度の変動が起こる可能性がある」と理解できます。
米国株指数のボラティリティ比較
S&P500
- 長期平均リターン:約7%(インフレ調整後)
- 年率ボラティリティ:15〜20%
- 例:2008年リーマンショック時には約-38%の下落、2020年コロナショックでは約-34%の下落
- 世界を代表する大型株中心で、中程度の変動幅
ナスダック総合指数
- テクノロジー株が多いためボラティリティは高め
- 長期ボラティリティ:20〜25%
- 例:2000年ITバブル崩壊時には約-78%の下落、その後回復までに15年以上
- 高成長企業に投資できる一方、上下動が激しい
ラッセル2000
- 小型株中心でボラティリティはさらに大きい
- 長期ボラティリティ:25〜30%
- 例:リーマンショック時には約-45%の下落
- 高リスク・高リターン志向の投資対象
ボラティリティを見る意味
ボラティリティは単なる数字ではなく、投資家がどの程度の変動を許容できるかを判断する材料です。
- 下落リスクを事前に把握できる
- 長期投資を続けるための心理的準備になる
- 債券や現金の比率を決める参考になる
- 「どの指数を軸にするか」の比較材料になる
例えばS&P500なら年間で20%下落する可能性は十分にあります。
1000万円投資していれば、短期的に200万円減ることもあるわけです。
数字として理解しておくことで、下落時にも冷静に対応できるようになります。
ボラティリティと長期投資の関係
短期的に見るとボラティリティは投資家を不安にさせます。
しかし長期で見れば、米国株インデックスは右肩上がりの成長を続けてきました。
- S&P500は過去50年間で平均年率約10%のリターン
- リーマンショック後の回復には約4年、コロナショックでは1年未満
- 長期投資では一時的な下落も「成長の途中の調整」として受け入れることが大切
さらに、積立投資を続ければボラティリティによる価格の上下がむしろ平均取得価格を下げる効果(ドルコスト平均法)につながります。
実践的なボラティリティ分析の使い方
- 過去の暴落局面を振り返り、自分が耐えられるか確認する
- ETFや投資信託の「リスク指標」や「最大下落率」をチェックする
- ボラティリティを「避けるため」ではなく「受け入れるため」に使う
- 投資を途中でやめないための心理的安全装置として活用
まとめ
株価指数のボラティリティは、リスクを数字で「見える化」する指標です。
S&P500、ナスダック、ラッセル2000はいずれも性質が異なり、リターンとリスクのバランスも違います。
長期インデックス投資では、ボラティリティを恐れるのではなく、想定したうえで投資を継続することが資産形成の王道です。
FAQ
Q1. ボラティリティが高い指数を選ぶと危険ですか?
必ずしも危険ではありません。高いリターンを得られる可能性がある一方、短期的な損失も大きくなります。自分のリスク許容度に合わせることが大切です。
Q2. S&P500とナスダック、どちらが長期投資に適していますか?
安定性を重視するならS&P500、成長性を重視するならナスダックです。ただしナスダックはボラティリティが高く、長期保有に心理的な負担がかかる場合があります。
Q3. ボラティリティはどのくらいの期間で見るべきですか?
過去1年や3年など複数の期間で確認すると良いです。短期的な数値に振り回されず、長期の平均を把握するのが現実的です。
Q4. 債券や現金を組み合わせるとリスクはどう変わりますか?
債券や現金を加えることでポートフォリオ全体のボラティリティは低下します。例えば株式100%よりも、株式70%+債券30%の方が標準偏差は小さくなります。
Q5. ボラティリティが低いファンドだけを選べば安心ですか?
短期的な値動きは穏やかになりますが、リターンも限定されます。長期的な資産形成では、適度なボラティリティを受け入れることが不可欠です。
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。