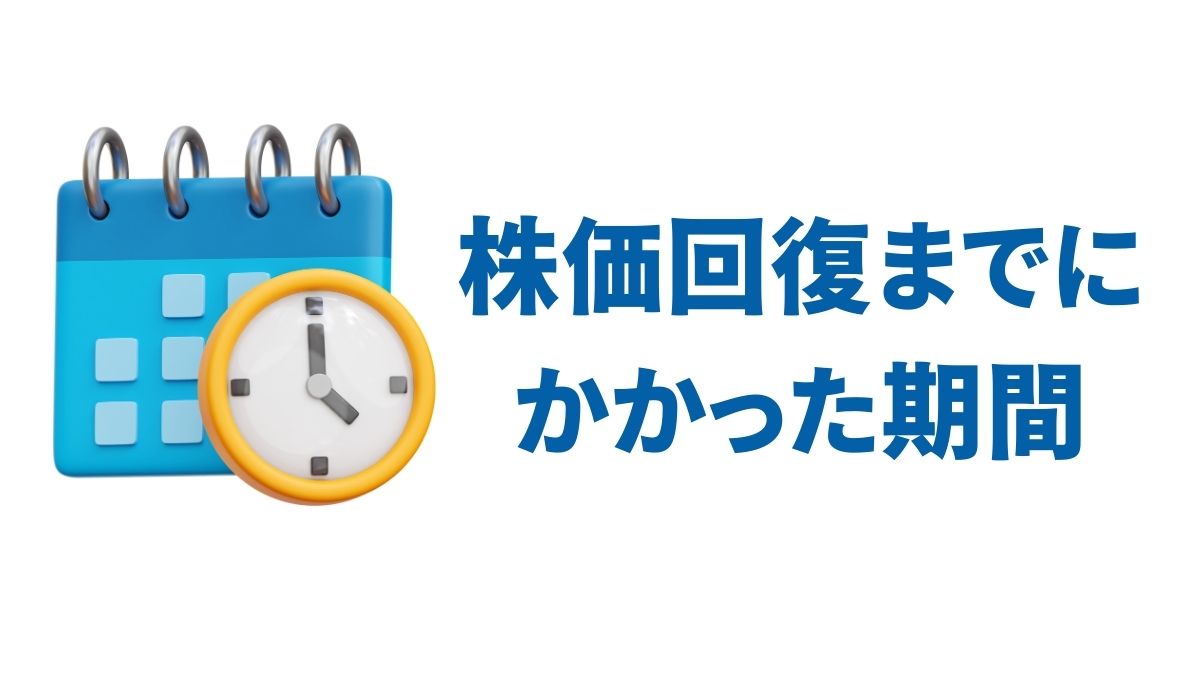
株価回復までにかかった期間の事例|SPY・QQQ・IWM・TLT・GLDの比較と投資の教訓
By Staff | 2025-08-22
Category: インデックス投資
投資を行う上で、多くの人が注目するのはリターンや下落幅ですが、それ以上に重要なのが「回復までの期間」です。
同じ-30%の下落でも、半年で戻る場合と10年以上かかる場合では投資家に与える心理的負担が大きく異なります。
長期投資においては、過去の下落からどの程度の時間で新高値を更新したのかを知ることが、資産配分の戦略を立てる上で大きな手がかりとなります。
SPY(S&P500 ETF)の回復期間
S&P500に連動するSPYは、米国を代表する株価指数として長期的な安定感があります。
リーマンショック(2007–2009)では約-56%の下落を記録しましたが、新高値を更新するまでにかかった時間はおよそ4年半。2007年10月の高値を超えたのは2013年3月でした。
- コロナショック(2020年2–3月)では1か月半で-33%下落しましたが、回復は非常に早く、わずか5か月で新高値を更新。2020年8月には下落前を超える水準に戻っています。
SPYは下落時に大きな調整を受けることもありますが、長期的な回復力の強さを示している代表的な例と言えるでしょう。
QQQ(NASDAQ100 ETF)の回復期間
ハイテク株中心のNASDAQ100に連動するQQQは、成長期待が高い一方で下落局面のダメージが大きくなる傾向があります。
ドットコムバブル崩壊(2000–2002)では-82%の大暴落となり、回復までにかかった期間はなんと15年。2000年3月のピークを取り戻したのは2015年に入ってからでした。
- 2022年の急激な利上げ局面では年間-33%の下落となりましたが、その後のテック株回復を受けて2023年半ばには大部分を戻し、完全回復までは約18か月で済みました。
このようにQQQは大きなリスクを伴うものの、成長局面では急速に回復する力を持っています。
IWM(ラッセル2000 ETF)の回復期間
中小型株に連動するIWMは、景気動向に敏感でボラティリティが高いETFです。
リーマンショック時には-59%の下落を経験し、ピーク回復までに6年かかりました。2007年の高値を取り戻したのは2013年初頭です。
- **コロナショック(2020年)**では-41%の急落を見せましたが、その後の景気刺激策により急回復し、10か月で新高値を更新。2021年1月には史上最高値に達しました。
IWMは下落が深いものの、景気拡大局面での反発が強烈であることが特徴です。
TLT(米国長期国債ETF)の回復期間
長期国債ETFのTLTは株式と逆相関で動くことが多いですが、金利動向に強く左右されます。
**リーマンショック時(2008年)**には株式市場が暴落する中で大きく買われ、短期間で高値を更新しました。株式が回復するよりも早く戻った資産のひとつです。
- しかし2020年の高値から2022年末までの急速な金利上昇局面では-46%下落し、その後も完全回復には至っていません。現在も回復には数年以上かかる可能性があり、債券もまた長期停滞のリスクがあることを示しています。
GLD(金ETF)の回復期間
安全資産として人気の高い金ですが、過去には長い低迷期もありました。
2011年の金価格ピークから2015年にかけて-45%下落し、再び高値を更新するまでには約9年を要しました。2011年につけた水準を再び突破したのは2020年のコロナショック後です。
- 一方で**コロナショック(2020年)**では株式市場が大きく下げる中、半年程度で上昇に転じて新高値を更新しました。
金は長期的に停滞するリスクもある一方、危機時には短期間で回復・上昇することがある典型的なヘッジ資産です。
回復期間から学べる教訓
- SPY:回復までの時間は比較的短く、長期投資に適した安定感
- QQQ:15年かかった停滞期もあるが、最近は成長力で急回復
- IWM:下落幅は大きいが、景気拡大期には強い反発を見せる
- TLT:株式と逆相関で早期回復することもあるが、金利上昇局面では長期停滞
- GLD:危機時には力を発揮するが、長期的に見れば回復まで数年単位が必要
資産ごとの特徴を理解することで、自分の投資戦略に合わせたポートフォリオ設計が可能になります。
まとめ
過去の事例が示すように、株価指数や資産クラスごとに「回復までにかかる時間」は大きく異なります。
SPYのように短期間で戻るものもあれば、QQQやGLDのように10年以上を要するものもあります。
投資において重要なのは、下落局面の深さだけでなく「回復までの時間」を理解し、それを織り込んだ資産配分を行うことです。
これにより長期投資をより安定的に続けることができるでしょう。
FAQ:株価回復期間に関するよくある質問
Q1. 株価の回復にかかる期間はどのように決まるのですか?
A. 回復期間は主に景気循環と金融政策に左右されます。景気後退が浅く金融緩和がすぐに実施される場合は数か月で回復することもありますが、金融危機やバブル崩壊のような深刻な局面では10年以上かかることもあります。
Q2. SPYはなぜ回復が比較的早いのですか?
A. S&P500は米国の大型優良企業で構成されており、業績回復力や資金流入の規模が大きいためです。金融危機やパンデミックのような大きな下落でも、米国経済全体の成長力が支えとなり、比較的短期間で新高値を更新する傾向があります。
Q3. QQQのように回復まで15年もかかったケースは特殊ですか?
A. ドットコムバブル崩壊後のQQQは、過剰なバリュエーションが長期停滞の要因でした。このような極端な事例は特殊ですが、「高成長株に集中している指数は回復に時間がかかるリスクがある」という教訓を示しています。
Q4. IWMの中小型株はなぜ回復に時間がかかるのですか?
A. 中小企業は資金調達力や国際競争力が大企業に比べて弱いため、不況期にダメージを受けやすいからです。その一方で、景気拡大局面では急成長する銘柄も多く、短期間で大幅に上昇する可能性を秘めています。
Q5. TLTやGLDは回復の動きが株式と違うのはなぜですか?
A. TLTは金利動向に強く依存し、FRBの政策次第で回復スピードが大きく変わります。GLDはインフレや金融不安で買われる一方、平常時には売られやすいため回復が長期化することがあります。それぞれ「株式とは異なる回復パターン」を持つため、分散投資に役立ちます。
Q6. 投資家はどの程度の回復期間を想定しておくべきですか?
A. 歴史的に見ると、株式市場では数か月で戻るケースもあれば10年以上かかるケースもあります。一般的には3~5年程度の回復期間を想定し、資産配分を調整するのが現実的です。短期的な下落を気にせず長期で投資を続けられるよう、リスク許容度に合ったポートフォリオを構築することが大切です。
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。