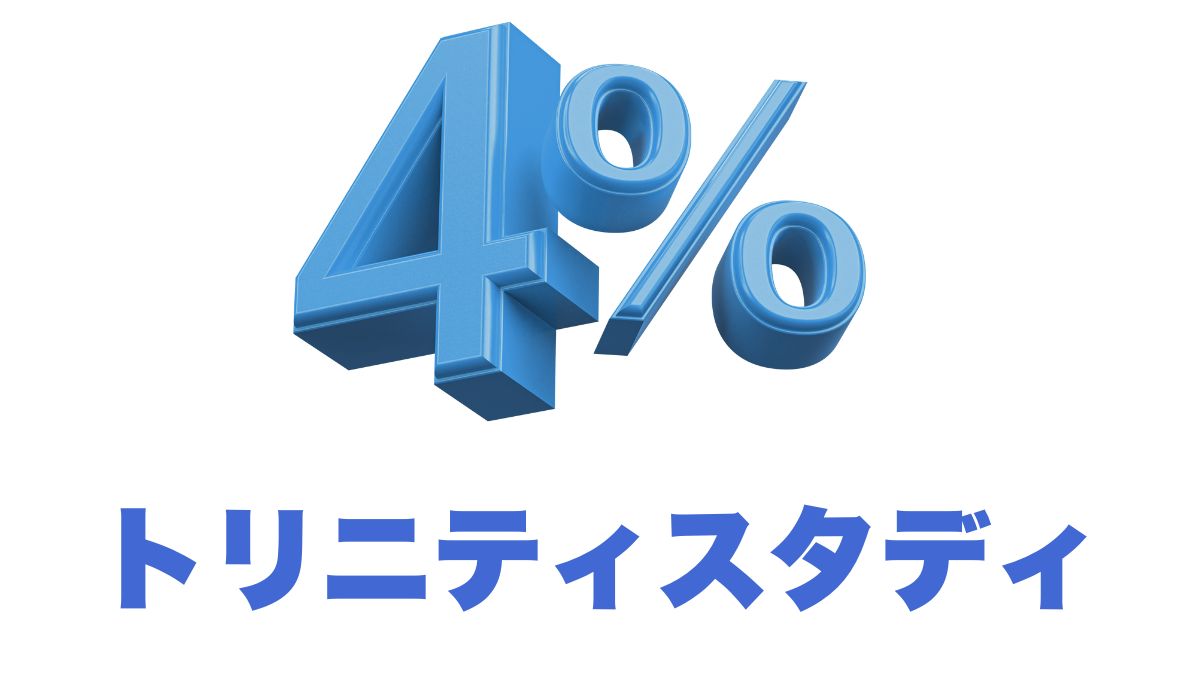定率 vs 定額シミュレーション|FIRE後の30〜50年を守る取り崩し比較
By Staff | 2025-09-30
Category: インデックス投資
FIREを達成した後、多くの人が最初に直面する課題は「どのように資産を取り崩すか」です。
インデックス投資を通じて築いた資産が十分にあったとしても、取り崩し方を誤れば想定より早く資産が尽きる可能性があります。
特に30〜50年という長期を生き抜く場合、その影響は決して小さくありません。
この記事では、代表的な方法である「定率取り崩し」と「定額取り崩し」を比較し、実際の数値を用いたシミュレーションを通して、それぞれの特徴やリスクを詳しく見ていきます。
定率と定額の基本的な仕組み
定率取り崩し
定率取り崩しとは、資産残高に対して毎年一定の割合を引き出す方法です。
たとえば1億円の資産を持ち、毎年4%を取り崩すとすると、初年度は400万円、翌年は資産の増減に応じて金額が変わります。
メリットは、資産が減れば取り崩し額も自動的に減るため、資産の枯渇リスクを軽減できることです。
ただし、不況時には生活費が大きく下がり、生活水準を調整しなければならない点がデメリットです。
定額取り崩し
一方、定額取り崩しは、資産の値動きにかかわらず毎年一定の金額を引き出す方法です。
例えば毎年400万円を取り崩すと決めた場合、資産が増えても減っても金額は固定です。
生活費を安定的に確保できる反面、資産が大きく減った時期でも同額を取り崩すため、資産寿命を縮めるリスクがあります。
特に初期に暴落が訪れると影響が深刻です。
シミュレーションの前提条件
シミュレーションを具体的にイメージするため、以下の条件を設定します。
- 想定期間:30年および50年
- 初期資産:1億円
- 投資対象:米国株インデックス(過去平均リターン年率6〜7%を想定)
- インフレ率:年率2%
- 生活費:400万円(初年度ベース)
定率取り崩しシミュレーション結果
仮に「毎年4%を取り崩す」とします。
初期資産は1億円、投資リターンは年率6%程度、インフレ率は2%を想定します。
初年度
1億円 × 4% = 400万円を取り崩し。残高は9600万円からスタート。
5年目
市場が堅調に推移したケースでは、資産は約1億1000万円に増加。
この年の取り崩し額は1億1000万円 × 4% = 440万円。
取り崩し額がインフレ上昇にある程度追随している。
10年目
資産が約1億2500万円まで成長した場合、取り崩し額は500万円。
初年度の400万円から比べて25%増加しており、インフレを考慮しても生活レベルを維持可能。
15年目
景気後退の影響で一時的に資産が9500万円まで下落したと仮定。
取り崩し額は9500万円 × 4% = 380万円に縮小。
この時期には節約や支出の調整が必要になるが、資産寿命を延ばす効果はある。
20年目
市場回復により資産は再び1億2000万円程度に戻る。
取り崩し額は480万円。長期的には再び生活費が安定。
25年目
資産は約1億3500万円に成長し、取り崩し額は540万円。
生活費はインフレで上がっているが、それに追いつく取り崩し額を確保できる。
このように定率取り崩しは、市場が好調なら取り崩し額も増え、不況期には自動的に取り崩し額が減少します。
資産寿命が尽きにくい安心感があり、実際に過去の米国株データを基にした研究では、4%ルールを守った場合、30年間の成功率は約95%に達するとされています。
ただし、この方法の難点は「生活費が市場の動向に左右される」点です。
例えば15年目のように暴落が来た場合、取り崩し額が減り、生活レベルを一時的に下げる必要が出てきます。
安定的な支出を重視する人にとってはストレスとなる可能性がありますが、長期的な資産維持には有効な戦略です。
定額取り崩しシミュレーション結果
次に「毎年400万円を固定で取り崩す」と仮定します。
初期資産は1億円、投資リターンは年率6%、インフレ率は2%を想定します。
初年度
400万円を取り崩し。残高は9600万円。生活費は市場環境に関係なく一定のため、安心感がある。5年目
市場が順調な場合、資産は約1億1500万円程度まで増加。
取り崩し額は毎年400万円固定なので、残高は安定して増える。
しかしインフレを考慮すると、400万円の購買力は実質的に約360万円相当まで低下。生活水準が少しずつ目減りするリスクがある。10年目
順調にいけば資産残高は約1億3500万円。
取り崩しは依然として400万円固定であり、資産に対する割合はわずか約3%まで低下。
資産の持続性は強まるが、インフレで400万円の実質価値は約330万円程度に縮小。生活費が足りないと感じる可能性が出てくる。15年目
もしここで景気後退が起こり、資産が9500万円に落ち込んだと仮定する。
それでも400万円を固定で取り崩すため、資産の減少スピードが速まる。
この時点で取り崩し割合は4.2%と上昇。市場回復が遅れれば資産寿命を削るリスクが大きくなる。20年目
市場回復で資産が再び1億2000万円前後に戻った場合でも、取り崩し額は400万円のまま。
資産余力は十分にあるが、20年のインフレを考えると、400万円の購買力は実質的に約270万円程度。
長期生活における「生活の質低下」という問題が浮かび上がる。25年目
資産残高は1億4000万円近くに増加する可能性もあるが、取り崩しは相変わらず400万円。
資産はむしろ余っているのに、購買力の低下で日々の生活が圧迫されているという「逆転現象」が起こる可能性がある。
このように、定額取り崩しは「生活費が一定で安心」という最大の強みを持つ一方で、以下の課題があります。
- インフレによって購買力が年々低下する
- 序盤に暴落があると資産寿命が一気に縮まる
- 長期になるほど、資産は余るのに生活の質は低下しやすい
リーマンショックのように序盤で40%以上の下落が発生した場合、残高が大きく減少しても400万円を引き出すため、資産寿命が30年持たないケースも想定されます
。
まとめると、定額取り崩しは「安定」と引き換えに「長寿リスク」「インフレリスク」に弱い戦略といえます。
順序リスクの影響
順序リスクとは、リターンの「順番」によって結果が大きく変わる現象です。
平均リターンが同じ6%でも、最初の10年で大幅に下落する場合と、後半に下落が来る場合では、資産寿命が大きく違ってきます。
定額取り崩しはこのリスクに特に弱く、暴落直後に取り崩しを続けることで資産が急速に減少する可能性があります。
一方、定率取り崩しは自動的に取り崩し額が減るため、順序リスクの影響をある程度和らげられます。
ハイブリッド戦略という選択肢
現実的には「定率か定額か」の二択ではなく、両者を組み合わせる方法も有効です。
- 最低限必要な生活費は定額で確保する
- それ以上の余剰部分は定率で調整する
- 取り崩し額に上限と下限を設けて幅を持たせる
例えば「毎年300万円は定額で確保し、追加で資産残高の2%を取り崩す」という形にすれば、安定性と持続性の両立が可能です。
日本で考慮すべきポイント
米国株インデックスに投資している場合、日本の投資家が直面する特有のリスクも考える必要があります。
- 為替変動:ドル建て資産を円に換える際のレート次第で取り崩し額が変動する
- 生活費インフレ:円建てでの物価上昇が資産寿命に与える影響
- 長寿リスク:日本の平均寿命は世界でも上位であり、50年以上の取り崩し期間を想定するのも現実的
Trinity Studyとの関連
米国で有名なTrinity Studyは、4%ルールの根拠として知られています。
これはまさに「定率取り崩し」の一例です。
ただし、研究の対象は主に米国の過去データであり、現在や将来の市場環境が同じ保証はありません。
したがって4%ルールは一つの目安にすぎず、実際には生活費や為替、インフレなどを加味して柔軟に調整する必要があります。
まとめ
FIRE後の資産寿命を守るには、取り崩し方の選択が重要です。
- 定率取り崩しは長期的に資産を維持しやすいが、生活費は市場に左右されやすい
- 定額取り崩しは生活の安定を得やすいが、資産寿命が縮むリスクがある
- 両者を組み合わせたハイブリッド戦略は、柔軟性と安定性を兼ね備えた現実的な方法
FIREを達成した後も安心して暮らし続けるためには、自身のリスク許容度やライフスタイルに合わせて取り崩し戦略を設計することが大切です。
さらに全体的な取り崩しの考え方や年齢別のシミュレーションについては、「FIRE後の取り崩し方法|インデックス投資で築いた資産を長持ちさせる戦略」 にまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。
関連記事
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。