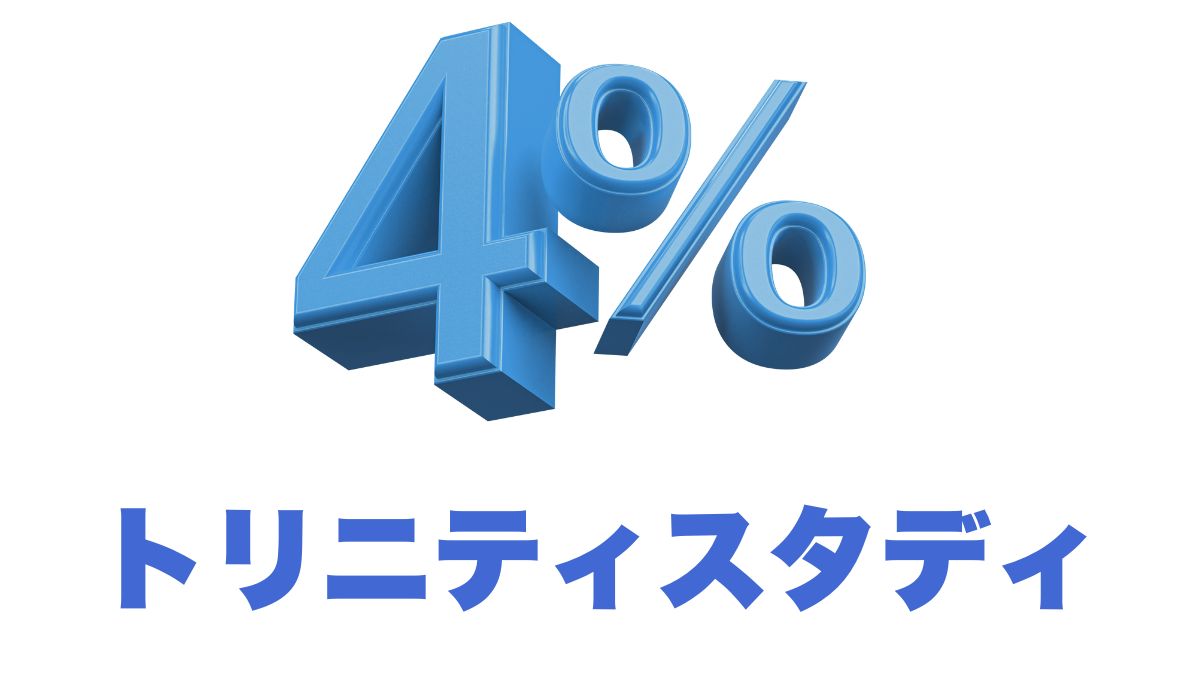
米国研究から学ぶ取り崩し戦略|トリニティスタディと4%ルールを日本でどう活かすか
By Staff | 2025-10-01
Category: インデックス投資
FIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指す際に多くの人が気にするのは、「資産をどのように取り崩せば寿命まで持たせられるのか」という点です。
その答えを示す一つの指標として有名なのが、米国で行われた「トリニティスタディ (Trinity Study)」と、そこから導き出された「4%ルール」です。
このルールはFIREを語る上で必ずと言ってよいほど登場しますが、前提や限界を理解せずにそのまま当てはめるのは危険です。
本記事ではトリニティスタディの概要と4%ルールを整理し、日本の投資家にとっての注意点や応用策を解説します。
1. トリニティスタディとは何か
トリニティスタディは、1998年に米国のTrinity Universityの教授陣によって発表された研究です。
- 対象:1926年〜1995年の米国株式・米国債データ
- 方法:ポートフォリオ(株式+債券)の比率を変えながら、30年間取り崩した場合に資産が枯渇しない確率をシミュレーション
- 結論:株式50〜75%、初年度4%を取り崩す戦略なら、30年間の成功率は95%前後
この結果はFIREムーブメントの基盤となり、「資産の4%を取り崩すなら30年間持続可能」と広まっていきました。
2. 4%ルールの基本
4%ルールはシンプルです。
- 初年度に総資産の4%を取り崩す(例:1億円なら400万円)
- 翌年以降はインフレ率を加味して取り崩し額を増やす
この仕組みにより、生活水準を安定させつつ資産寿命を守れるという考え方です。
実際、米国市場のデータでは30年間で非常に高い成功率を記録しました。
3. Trinity Studyの前提と限界
Trinity StudyはFIREの取り崩し戦略を考える上で非常に有名な研究ですが、前提条件を理解せずにそのまま適用するのは危険です。
まず、この研究は米国市場のデータを前提にしているため、高い株式リターンを背景にしています。
米国株を中心に投資する日本人投資家にとって参考にはなりますが、他市場に当てはめるのは難しいという点は知っておくべきでしょう。
次に、分析期間が30年に限定されていることが大きな制約です。
日本のように平均寿命が長い国では、40〜50年のFIRE生活を想定する必要があります。
30年で安全とされた取り崩し率が、より長期で同じように機能するとは限りません。
さらに、税制の違いも重要です。
トリニティスタディは税引き前のリターンで計算されていますが、日本では配当課税や譲渡課税が加わるため、実際に使える資金はシミュレーション結果より少なくなります。
また、支出の固定性という点も現実とは異なります。
研究では毎年インフレ調整後の一定額を取り崩す前提でしたが、実際の生活費は変動します。
旅行や医療費で大きく増える年もあれば、抑えられる年もあります。
要するにトリニティスタディは「米国株+30年+税引き前+一定支出」という条件下で導かれた結果であり、日本人投資家が利用する際には期間や税制、支出の変動を考慮して調整する必要があります。
4. 日本人投資家にとっての注意点
日本で4%ルールをそのまま使う場合には、いくつか特有のリスクに注意が必要です。
まず大きいのは為替リスクです。米国株を中心に運用していると、ドル建てでは資産が安定していても、円に換算したときに円高が進めば資産価値は目減りしてしまいます。
FIRE後の生活費が円建てで必要な以上、この為替変動は無視できません。
次に税制の違いも大きなポイントです。
米国の研究では税引き後を考慮していませんが、日本では配当課税や譲渡課税がかかるため、取り崩し可能な実際の金額は想定より少なくなります。
特に高配当株や頻繁な売却を前提とする場合、税負担は資産寿命に大きな影響を与えるでしょう。
さらに社会保険料や医療費といった支出は、日本特有の固定費として考慮すべきです。
FIRE後でも国民健康保険料や介護保険料は継続して発生し、加齢とともに医療費の負担は増える傾向にあります。
これらは生活費に組み込み、資金計画に反映する必要があります。
最後に、日本は世界有数の長寿国である点も無視できません。
米国のTrinity Studyが前提とした30年の取り崩し期間では足りず、40年から50年の長期を想定する必要があります。
取り崩し率を抑えたり、資産配分を工夫したりすることで、この「長寿リスク」に備えることが求められます。
5. 代替戦略・応用的な考え方
4%ルールを参考にしつつ、日本では以下のような応用が現実的です。
- 3%ルール:取り崩し率を3%程度に抑えることで、長寿リスクや市場不調に備える
- 定率取り崩し:毎年資産の一定割合(例:3.5%)を取り崩すことで、市場環境に応じて支出が変動
- バケット戦略:短期(現金)、中期(債券)、長期(株式)で資産を分け、暴落時の生活費を守る
- 可変支出戦略:市場が悪いときは旅行や娯楽を減らし、資産を守る柔軟性を持つ
6. シミュレーション比較
ここで、簡単なシミュレーションを紹介します。
- 前提:初期資産1億円、年率リターン4.5%、インフレ2%、期間30年
- ケースA:4%ルール
- 初年度400万円、以降インフレ調整
30年後も資産は残るが、成功率は市場環境に左右される
ケースB:3%ルール
- 初年度300万円、以降インフレ調整
- 資産の減りは緩やかで、40年〜50年持つ可能性が高い
米国の研究では4%で十分でしたが、日本の長寿・税制・為替リスクを踏まえると、3%程度を目安にする方が安心度は高まります。
まとめ
トリニティスタディと4%ルールは、FIRE後の取り崩し戦略における「出発点」として非常に有用です。
しかし、米国市場という前提条件をそのまま日本に当てはめるのは危険です。
日本の投資家にとって重要なのは、
- 為替や税制、医療費など日本特有のリスクを考慮すること
- 期間を30年ではなく40〜50年と想定すること
- 4%を参考にしつつ、3%ルールや可変戦略で柔軟に対応すること
FIREは数字のマジックではなく、現実的な生活とのバランスで成り立ちます。
米国の研究を「基準」として学びつつ、自分自身の環境に合わせて取り崩し戦略を設計することが、安心して長く暮らすための鍵となるでしょう。
また、取り崩しの基本戦略やキャッシュフロー管理を含めた全体像については、「FIRE後の取り崩し方法|インデックス投資で築いた資産を長持ちさせる戦略」 で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
関連記事
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。

