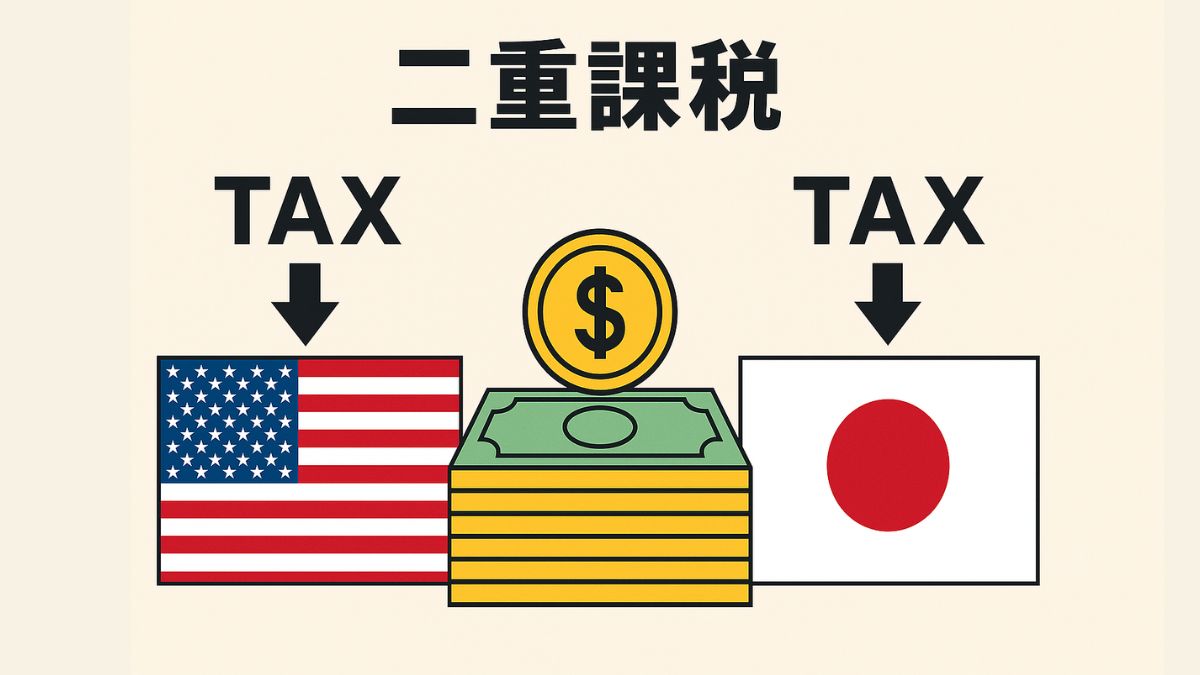米国ETFと日本投資信託の課税比較|長期投資における違いを徹底解説
By Staff | 2025-10-02
Category: インデックス投資
インデックス投資をする際、多くの投資家が選択肢に入れるのが 米国ETF と 日本籍の投資信託 です。
どちらも長期投資に活用できる有力な商品であり、同じ指数に連動する商品でも最終的なリターンに大きな差が出ることは少ないでしょう。
しかし、課税の仕組みには見逃せない違いがあります。
特に 配当課税の扱い、二重課税の有無、そして 外国税額控除が利用できるかどうか といった点は、長期的な資産形成の効率に影響します。
配当金が直接投資家に入るのか、それともファンド内で再投資されるのかによって、複利効果や税負担が異なるためです。
長期投資家にとって最も大切なのは「投資を続けられる仕組みを選ぶこと」です。
本記事では、米国ETFと日本投資信託の課税面を比較し、それぞれの特徴を整理していきます。
仕組みを理解することで、自分に合った投資スタイルをより安心して継続できるようになるでしょう。
日本の投資信託の課税の仕組み
日本籍の投資信託は、日本国内の法制度に基づいて運用される商品です。
投資信託が米国株を保有している場合、配当には米国源泉税10%がファンド内で自動的に差し引かれます。
投資家はこれを取り戻す手段(外国税額控除)を持たず、そのままコストとして吸収されます。
その一方で、分配金は多くの場合ファンド内で再投資され、投資家自身に直接支払われないため「課税繰延効果」があります。
つまり、保有中に毎回課税されるのではなく、売却や解約のタイミングで利益が確定したときにまとめて課税される仕組みです。
このため、複利効果を最大限活かせるのが特徴です。
売却益に対しては日本の金融所得課税が適用され、20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が課されます。
外国税額控除の処理はファンド内部で完結し、投資家が個別に申告して取り戻すことはできません。
米国ETFの課税の仕組み
一方、米国ETFはアメリカで設定されたファンドを日本から直接購入する商品です。
日本の証券会社を通じて投資することは可能ですが、課税の仕組みは国内投資信託と異なります。
まず、米国ETFの配当には米国源泉税10%が課されます。
その後、日本でも20.315%の課税がかかるため、配当部分については二重課税のように見える仕組みになります。
ただし、日本の税制では「外国税額控除」を利用することで、この二重課税分を一定程度取り戻すことができます。
売却益については米国では課税されず、日本国内で20.315%が課されます。
配当課税が「ファンド内で繰延」される日本投資信託と違い、米国ETFでは投資家に直接課税が来る点が大きな違いです。
二重課税と外国税額控除
米国ETF投資家にとって気になるのが、配当にかかる二重課税です。
- 米国での源泉徴収:10%
- 日本での課税:20.315%
例えば、米国ETFから年間10万円の配当を受け取った場合、まず米国で1万円が源泉徴収され、残り9万円が日本で課税対象になります。
9万円に対して20.315%課税されるため約1.8万円が課税され、最終的に手元に残るのはおよそ7.2万円となります。
このとき、確定申告で外国税額控除を利用すれば、米国で支払った1万円の一部を日本の税額から差し引くことが可能です。
実際にどの程度控除されるかは個々の税務状況に左右されますが、条件が整えばすべてが控除可能となるケースもあります。
日本投資信託の場合、ファンド内で外国税が処理されるため、投資家が申告する必要はありません。
この点は「シンプルさ」というメリットになります。
NISA・iDeCoでの扱いの違い
非課税制度であるNISAやiDeCoでは、米国ETFと日本投資信託での扱いにも違いがあります。
NISAの場合
- 日本投資信託:売却益・分配金ともに非課税
米国ETF:日本国内課税は非課税だが、米国源泉税10%は免除されない
iDeCoの場合
- 商品ラインナップは基本的に日本投資信託中心
- 運用益は非課税で再投資される
米国ETFを直接選べるケースは少なく、ほとんどが国内投信経由
つまり、NISAでは「米国ETFだと米国源泉税が残る」、iDeCoでは「そもそも米国ETFが選べない」ケースが多いのが実態です。
実際の税負担シミュレーション
ここで、日本投資信託と米国ETFを比較した簡単なシミュレーションを見てみましょう。
米国ETFの場合
年間配当10万円 → 米国源泉税1万円 → 残り9万円に国内20.315%課税(約1.8万円) → 手取りは約7.2万円。
確定申告で外国税額控除をすれば、米国源泉税1万円の一部を取り戻せる可能性あり。
日本投資信託の場合
投資信託が米国株を保有している場合、配当には同様に米国源泉税10%がファンド内で自動的に差し引かれます。
ただし、これは投資家個人が外国税額控除を利用することはできず、そのままコストとして組み込まれます。
そのうえで配当はファンド内で再投資されるため、投資家は売却時まで課税を繰り延べられるのが特徴です。
売却時に利益が出れば20.315%が課税されますが、保有中は複利効果を損なわずに運用できる点がメリットです。
長期投資の観点から見た課税の違い
インデックス投資の本質は「長期で市場に居続けること」にあります。
そのため、課税の仕組みが長期リターンにどう影響するのかを理解することは重要です。
米国ETFと日本投資信託はどちらも同じ指数に連動できますが、課税タイミングや税処理の違いが複利効果に与える影響は無視できません。
1. 課税タイミングの違いと複利効果
米国ETF:配当が発生するたびに米国源泉税10%が差し引かれ、日本でも課税対象になります。外国税額控除を利用すればある程度取り戻せますが、課税は定期的に発生するため、再投資に回せる額はその分少なくなります。結果として、長期的には複利の積み上げがわずかに削られることになります。
日本投資信託:配当はファンド内で再投資され、投資家に直接支払われないため、保有中は課税されません。売却時にまとめて課税される「課税繰延効果」があるため、その間は本来払うはずだった税金分も運用に回り、複利効果をフルに活かせるという強みがあります。
2. 制度利用との相性
NISAやiDeCoのような非課税制度では、日本投資信託の方が制度メリットをフルに享受しやすいのが実態です。米国ETFをNISAで保有しても米国源泉税10%は残ってしまうため、完全な非課税にはなりません。
逆に課税口座であれば、米国ETFは信託報酬が低いため、運用コストの面で優位に立つケースがあります。
3. 長期的な投資行動への影響
投資のゴールは「安心して続けられること」です。
課税処理がシンプルで手間の少ない日本投資信託は、初心者や税務申告に不安がある人に向いています。
一方で、米国ETFはコストを重視し、確定申告や外国税額控除を含めて積極的に管理できる投資家に適しています。
まとめ
米国ETFと日本投資信託は、どちらも長期インデックス投資に活用できる選択肢ですが、課税面では次のような違いがあります。
米国ETF:低コスト・透明性が高い一方で、配当に米国源泉税10%がかかり、その後日本でも課税されます。ただし、確定申告を行えば外国税額控除で一部を取り戻すことが可能です。
日本投資信託:米国株を組み入れている場合、ファンド内で米国源泉税10%が差し引かれます。ただし投資家自身が外国税額控除を行うことはできません。その代わり、配当は再投資されるため課税は売却時まで繰り延べられ、運用中は複利効果を活かせるのが特徴です。
NISA・iDeCo:制度の性質上、日本投資信託の方がメリットを享受しやすいケースが多い一方で、米国ETFでは米国源泉税分が必ず残ります。
どちらを選んでも「長期投資の基本」が変わるわけではありません。
制度やコスト、課税の仕組みを理解したうえで、自分にとって安心して続けられる商品を選ぶことが大切です。
税制を正しく理解すれば、より納得感を持って長期投資を継続できるでしょう。
加えて、NISA・iDeCoの仕組みや外国税控除、損益通算など、インデックス投資の税金全般を整理した総合解説も用意しています。
詳しくは インデックス投資の税金と節税方法まとめ|NISA・米国ETF・外国税控除まで徹底解説 をご覧ください。
関連記事
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。