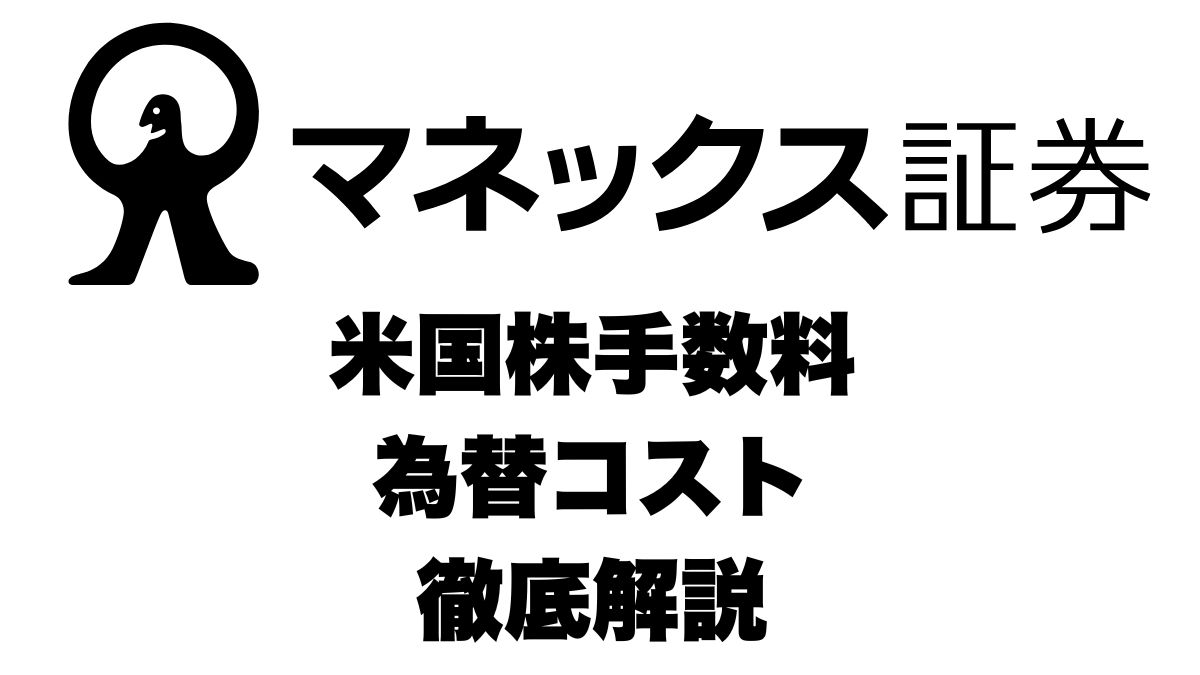米国株手数料の比較表|楽天・SBI・マネックス・松井の違い
By Staff | 2025-10-06
Category: インデックス投資
米国株投資を始める際に、多くの人がまず考えるのは「どの証券会社を使えばコストを抑えられるか」という点です。
ここ数年で各社が激しい競争を繰り広げた結果、売買手数料や為替コストは大幅に引き下げられ、主要ネット証券の間で大きな差はほとんどなくなりました。
実際、どの会社を選んでも投資を続けられる環境は十分整っていると言えます。
ただし、手数料以外の細かな条件や仕組みには違いが残っています。
例えば「NISAでの無料化の範囲」「為替の扱い方」「ポイント連携」といった点は証券会社ごとに特色があり、自分の投資スタイルによって感じる利便性は変わってきます。
また、口座数や利用者数といった規模の大きさも安心感につながる要素のひとつです。
この記事では、楽天証券・SBI証券・マネックス証券・松井証券という主要4社を取り上げ、それぞれの特徴や違いを整理したうえで、どんなタイプの投資家に向いているのかを解説します。
各社の米国株手数料と為替コスト
まずは、4社の基本的なコストを整理してみましょう。
楽天証券
売買手数料は約定代金の0.495%で、上限は22ドル。為替コストは25銭ですが、楽天銀行を併用すれば引き下げ可能です。NISAの成長投資枠では買付手数料が無料となります。SBI証券
売買手数料は0.45%で、上限は20ドルと他社よりわずかに安い水準。為替コストは通常25銭ですが、住信SBIネット銀行を使えば1ドルあたり4〜6銭に抑えられます。新NISAでは成長投資枠で買付手数料が無料です。マネックス証券
売買手数料は0.495%で上限22ドル。他社との違いは円貨決済で米国株を買う場合、為替コストが0銭になる点です。さらに「米国ETF買い放題プログラム」を利用すれば、対象ETFの買付手数料がキャッシュバックされます。松井証券
売買手数料は0.495%で上限22ドル。最低手数料は0ドルのため、小口投資にも対応しやすいのが特徴です。最大のポイントは円⇄ドル両替が恒久的に0銭であること。新NISA口座では米国株やETFの売買手数料が無料です。
こうして比べると、コスト面ではどの証券会社も差が縮まっていることが分かります。
その中で、松井とマネックスは「為替0銭」という点で特に強みを発揮しています。
楽天証券の特徴
楽天証券は利用者数が1,200万口座を超える大手で、SBI証券に次ぐ規模を誇ります。
- 売買手数料は0.495%(上限22ドル)
- 為替コストは25銭(楽天銀行連携で低減可能)
- 新NISA口座の成長投資枠で買付手数料無料
また、楽天経済圏との親和性が高く、楽天カードや楽天銀行との連携、さらには楽天ポイントを使った投資が可能です。
日常生活で貯めたポイントをそのまま投資に回せる点は、他社にはない魅力といえます。
SBI証券の特徴
SBI証券は1,400万口座を超え、国内最大規模の証券会社です。
幅広い商品ラインナップや使いやすい取引ツールに加え、積極的なコスト削減策「ゼロ革命」を展開しています。
- 売買手数料は0.45%(上限20ドル)と主要ネット証券で最安水準
- 為替コストは25銭だが、住信SBIネット銀行経由で4〜6銭まで下げられる
- 新NISA口座では成長投資枠で買付手数料が無料
ただし注意点として、為替コストが完全無料になるわけではなく、松井やマネックスと比べると「ゼロ」のインパクトはやや弱まっています。
それでも総合力では国内随一の地位を保っています。
マネックス証券の特徴
マネックス証券は、円貨決済0銭というユニークな仕組みを導入しています。
日本円のままS&P500や全米株ETFなどを買付しても余計な為替コストが発生しないため、初心者でも分かりやすい点が魅力です。
- 売買手数料は0.495%(上限22ドル)
- 円貨決済の買付時は為替コスト0銭
- 「米国ETF買い放題プログラム」で対象ETFの手数料をキャッシュバック
また、配当をドルで受け取ってそのまま再投資することも可能で、外貨派にとっても使いやすいサービス設計になっています。
松井証券の特徴
松井証券は老舗でありながら、思い切ったコスト削減を進めている点が評価されています。
- 売買手数料は0.495%(上限22ドル、最低0ドル)
- 円⇄ドル両替は恒久的に0銭
- 新NISA口座では米国株・ETFの売買手数料無料
為替コストが恒久的に無料であるのは松井ならではの強みで、円貨派・外貨派どちらにとっても使いやすい仕組みです。
少額投資にも対応しているため、初心者が最初の一歩を踏み出すのにも適しています。
投資スタイル別おすすめ証券会社
投資家のスタイルによって選ぶべき証券会社は変わってきます。
- 安心感を重視したい場合
SBI証券(1,400万口座)と楽天証券(1,200万口座)の二強は、利用者数が多く、システムの安定性やサポート体制に優れています。
- 為替コストを抑えたい場合
松井証券(円⇄ドル両替恒久0銭)やマネックス証券(円貨決済0銭)が最有力です。
- コストを最小化して積立を続けたい場合
松井の「為替0銭+NISA無料」、マネックスの「円貨0銭+ETFキャッシュバック」が長期投資には魅力的です。
- 楽天経済圏を活用したい場合
楽天ポイントをそのまま投資に回せる楽天証券が最適です。
まとめ
主要ネット証券4社はそれぞれ異なる強みを持ち、米国株投資のコストを大幅に引き下げています。
SBIと楽天は口座数の規模で圧倒的な存在感を示し、安心感を提供しています。
一方、マネックスと松井は為替コストや手数料のゼロ化施策を進め、差別化を図っています。
特に「為替0銭」の仕組みを導入した松井とマネックスの登場により、円貨派でも外貨派でも低コストで米国株投資を続けられる環境が整いました。
最終的には、コストを重視するか、安心感を優先するか、あるいは日常生活のポイント活用を軸にするかといった、自分自身の投資スタイルに合わせて証券会社を選ぶことが重要です。
あわせて、売買手数料・為替コスト・NISA対応といった全体像を整理したい方は、以下の記事もご覧ください。
米国株取引コスト・手数料完全ガイド|主要ネット証券を徹底比較
関連記事
マーケット概況
最新記事
カテゴリー
タグ
個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT
投資忍者 プロフィール
米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。
「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。
元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。